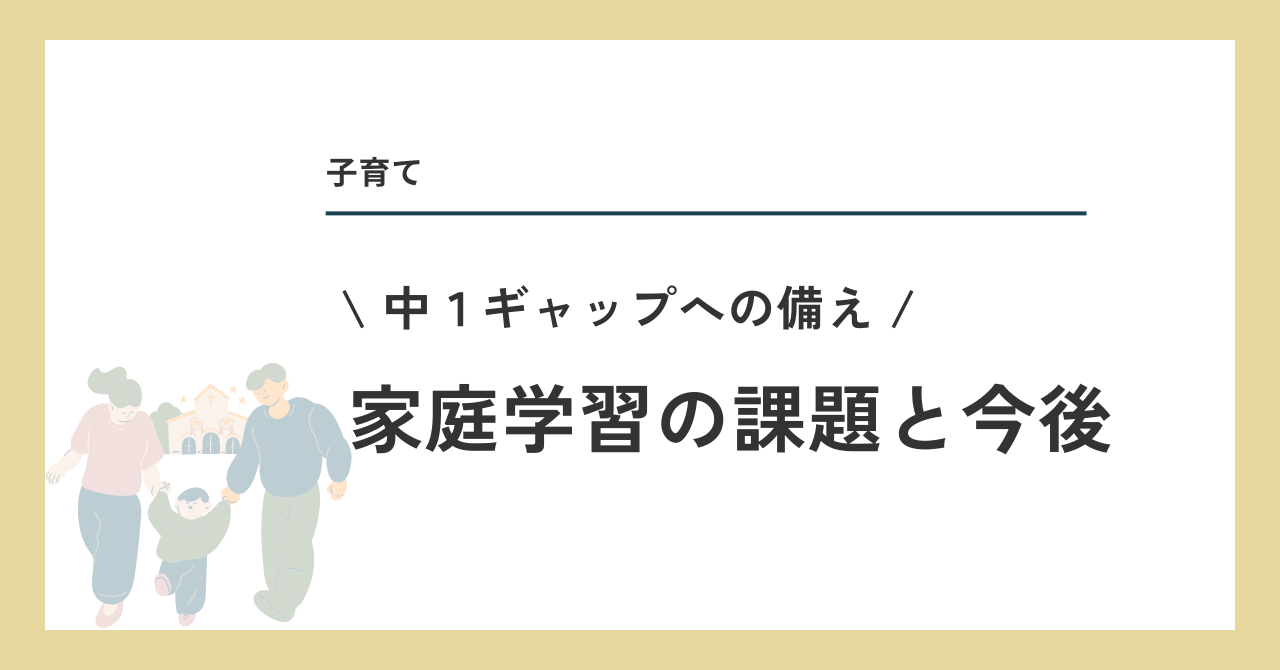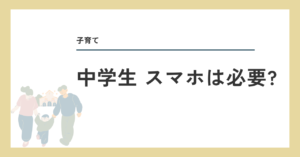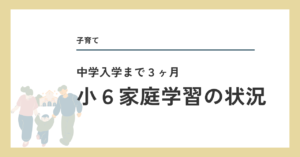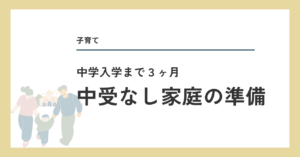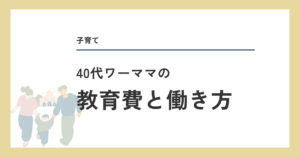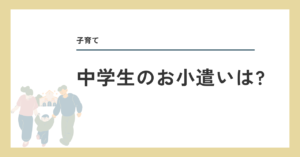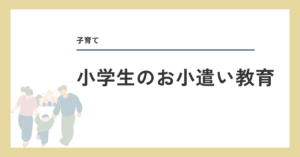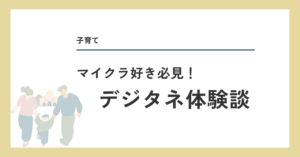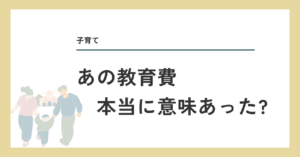はじめに
小5の終わりからスタートした家庭学習。
前編では家庭学習の習慣づけ、中編では目的の共有や科目ごとの準備について書きました。
後編では、実際に数か月家庭学習を続けてみて見えてきた課題と、わが家で意識した親のスタンスについてまとめます。
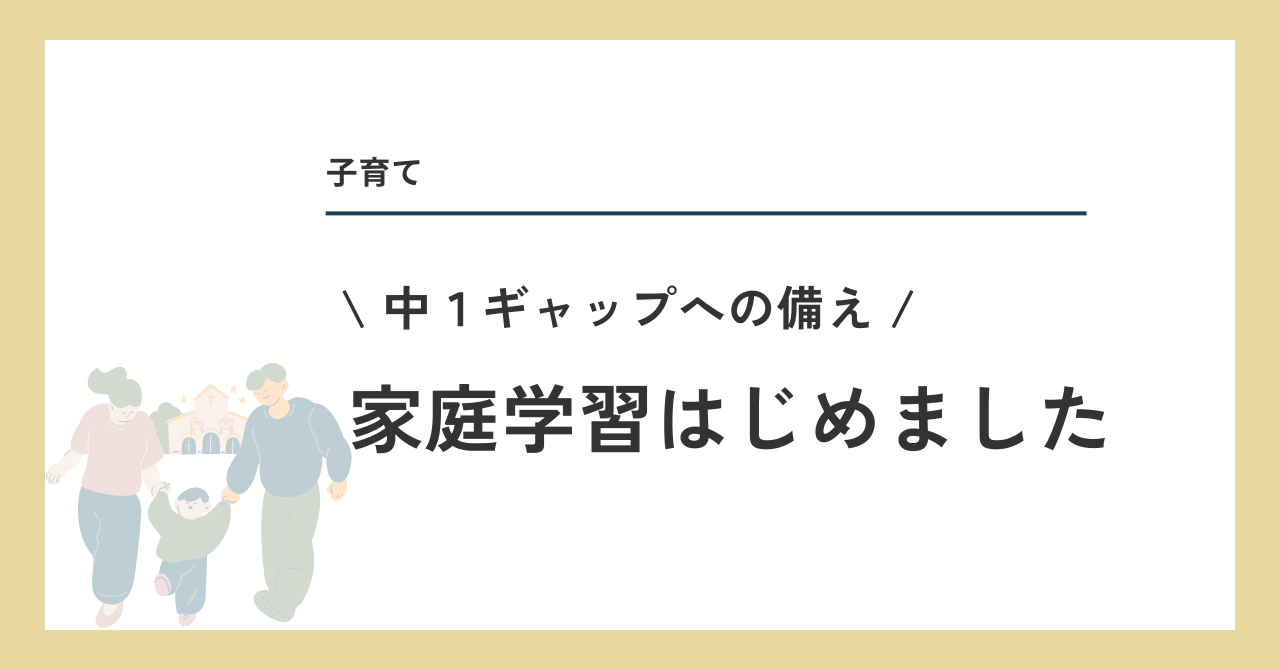
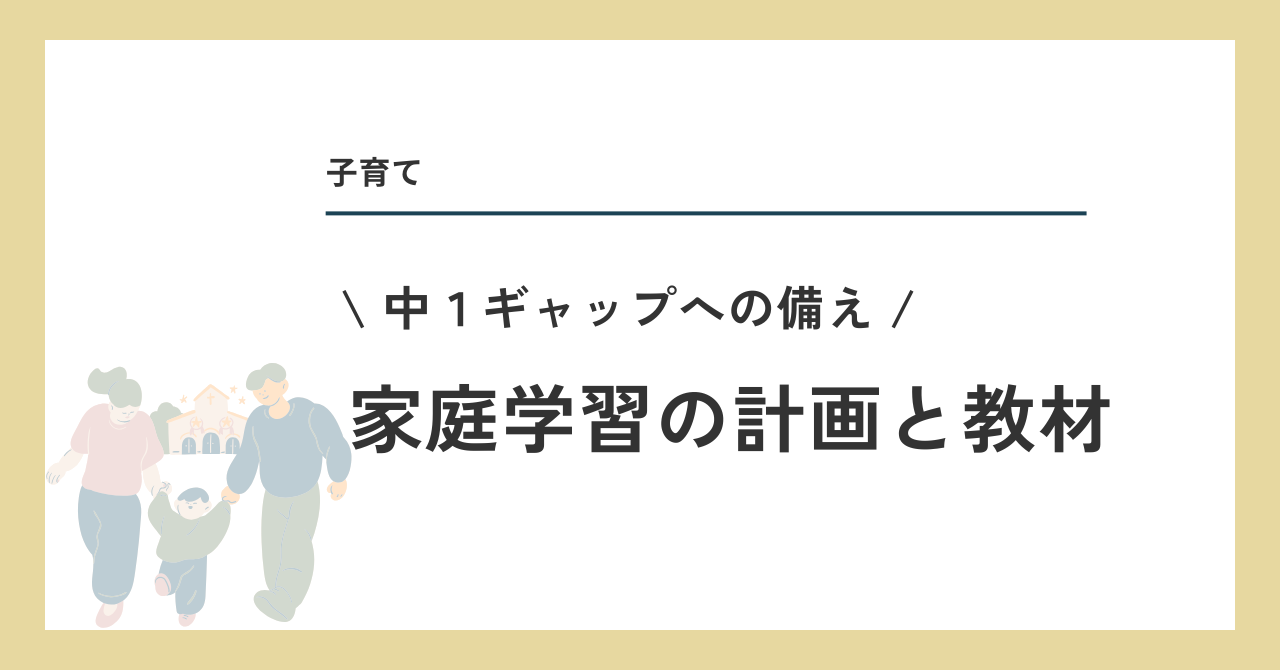
見えてきた課題

毎日は無理…
スタート前から「習い事の予定も多いし、できない日もあるだろうな」と思っていました。
実際にやってみると、習い事のほか、学校の予定や本人の気分などでやれない日も出てきました。やっぱり毎日続けるって難しい。
でも、平均して週4〜5回続けられています。予定通りではなくとも、続けられたこと自体が大きな一歩。
「できなかった日」より「できた日」に目を向けて、「少しずつ定着してきてるな」と自分にも子どもにも言い聞かせています。
一日30分、全然進まない…
毎日、始める前に「今日はここと、ここを…」といった感じで、私がやる内容を決めています。
が、これが まぁ思う通りに進まない!
途中でわからない単語を調べたり、間違えた問題を解き直したり。
今は慣れましたが、最初のころは「思っていた半分も進まない・・・」という感覚でした。
でも、わからない単語や間違いを放置してしまっては意味がない。
それに、家庭学習ゼロからスタートの息子には高いハードルは無理なので、「まずは30分をこつこつ続けること」を目標に頑張っています。
やる気は基本ない。けど、ゼロでもない
うちの子は、いわゆる「自ら進んで前向きに学習に取り組むタイプ」ではありません。
「え〜今日もやるの〜」という空気を出してくる日も多々あります。笑
ただ、それでも「やらない!」と拒否することはないし、たまに「なんか前より計算早くなったかも」とつぶやくこともある。小さな実感の積み重ねが、「やる意味あるかも」という感覚につながっているなら、それで十分です。
親が主導しすぎていない?と自問する
使う教材も、その日の内容も、今のところすべて私(親)が決めています。日々の30分が「親の指示で動く時間」になってしまっている感は否めません。
正直、それでいいのか?と悩むこともあります。
少しずつ、自分で考えて決める経験を増やせるように、夏休みの取り組みテーマにしたいところです。
英語が原点だったのに、時間を割けていない現実
そして一番の想定外はここ。
この家庭学習を始めた一番のきっかけは「中1英語への不安」でした。
でも、実際にやってみると、算数や国語の基礎に思った以上の穴があることに気づき、そちらに時間を取られがちに。さらに英語は継続と積み上げが大事なので、時間が確保しづらいのも事実…。
英語は夏休みを使ってもう一度立て直そうと考えています。
夏休みに向けた短期的目標
これまで、学習の段取りは私がしてきました。
でも、中学に向けては、少しずつでも「自分で決める」経験が必要だと感じています。
夏休みは、生活のリズムも自分で作れる貴重な期間。勉強の計画だけでなく、遊びや習い事、家のお手伝いも含めて、自分の予定を立ててみる練習をしたいと思っています。
とはいえ、いきなり「全部自分で決めてやってね」ではハードルが高いと思うので、最初は親子で一緒に。
今、ちょうどその話をしているところなのですが、息子の反応は
 息子
息子お母さん、またなんか言ってんな・・・
といった感じ。
まずは「計画を立てるってどういうことか」を一緒に体感することが目標です。
📌この取り組みは、以下の記事で紹介しています。
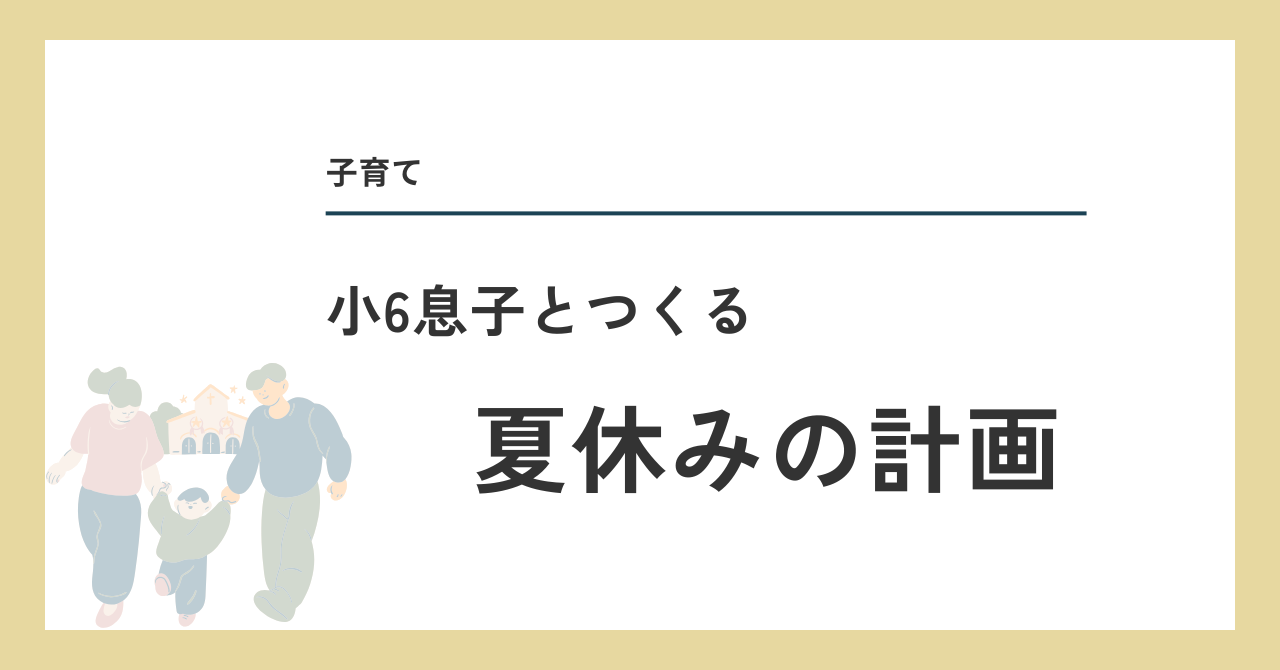
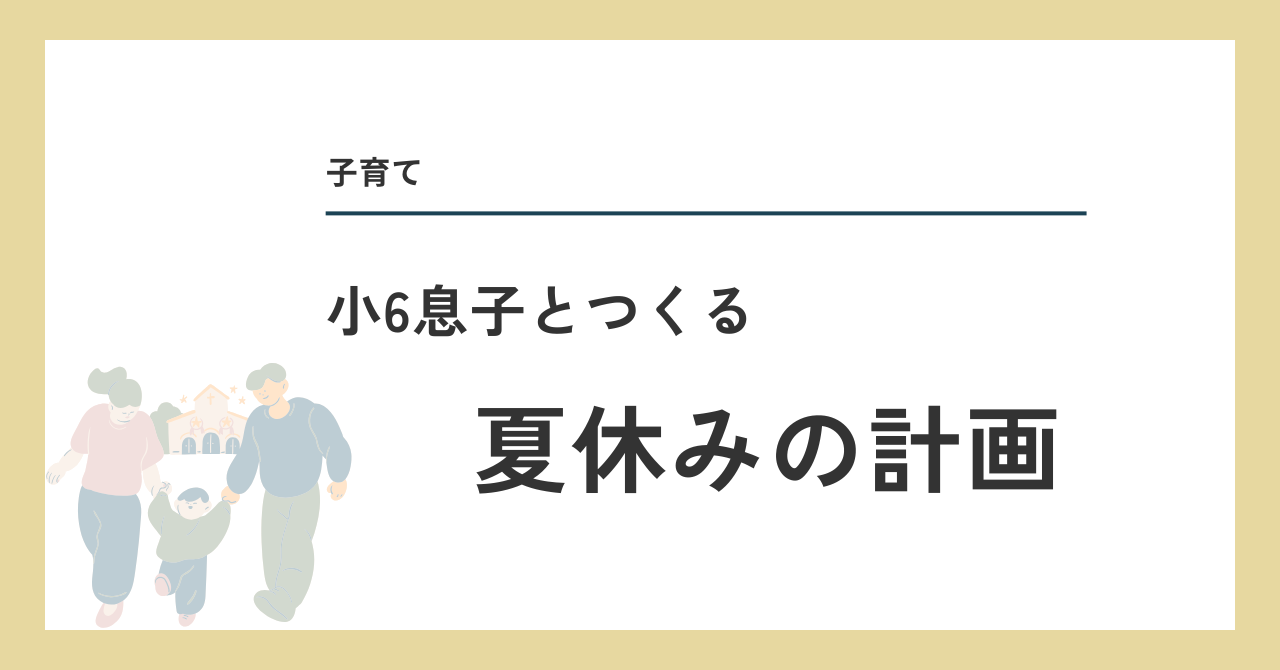
中学に向けた中期的な見通し
ここでは、中学以降を見据えて大切にしたいことと、親としてどんなスタンスで関わりたいかについて、私なりに考えていることをまとめてみました。
学習の伴走はいつまで?
今は遅ればせながら家庭学習を開始したばかりで、親が密に伴走しています。
ですが、中学に行ってもず~っと伴走、っていうのもないような…。
現時点でのざっくりしたイメージとしては、以下のような流れで少しずつ親の関りを減らしていけたらな、と考えています。
- 中1の前半(4〜7月):親と一緒に定期テスト対策の方法を探る
- 中1の後半(9月以降):徐々に自分で計画を立てて、親はサポート役へ
- 中2以降:必要なときだけ親が助言。自分の学習スタイルを確立する
もちろん、計画通りにはいかないと思いますし、反抗期や部活との両立など、新たな壁も出てくるはず。
でも「自分で自分を管理できる力を育てる」ことは、今から意識しておきたい中期的な目標です。
塾は「中3から」を基本方針に。でも柔軟に考える
わが家の方針としては、中3まではできれば塾なし、で進めたいと考えています。
その理由は、
- 家庭での学習スタイルを整える経験をしてほしい
- 週の予定が詰まりすぎると、日々の余裕がなくなる
- 息子自身が塾より家でやる方が良いというタイプ
といったところです。
ただ、無理に家庭だけで抱え込むつもりはありません。
「やっぱり外の力を借りた方がよさそう」と思えば、すぐに動けるよう柔軟に考えています。
おわりに
この数ヶ月、家庭学習を続けてきて感じたのは、「勉強の中身も大事だけど、もっと大事なのはどのように学ぶか」ということでした。
今はまだ、親が主導して、声をかけて、内容を決めています。
でも、最終的には「自分で、管理できる人」に育ってほしい。そのためには、親がいつか「教える」から「見守る」へと役割を変えていく必要があるそう感じています。
今回の記事が、わが家の試行錯誤の記録として、誰かのヒントになれば嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
👉子育てのまとめページはこちら