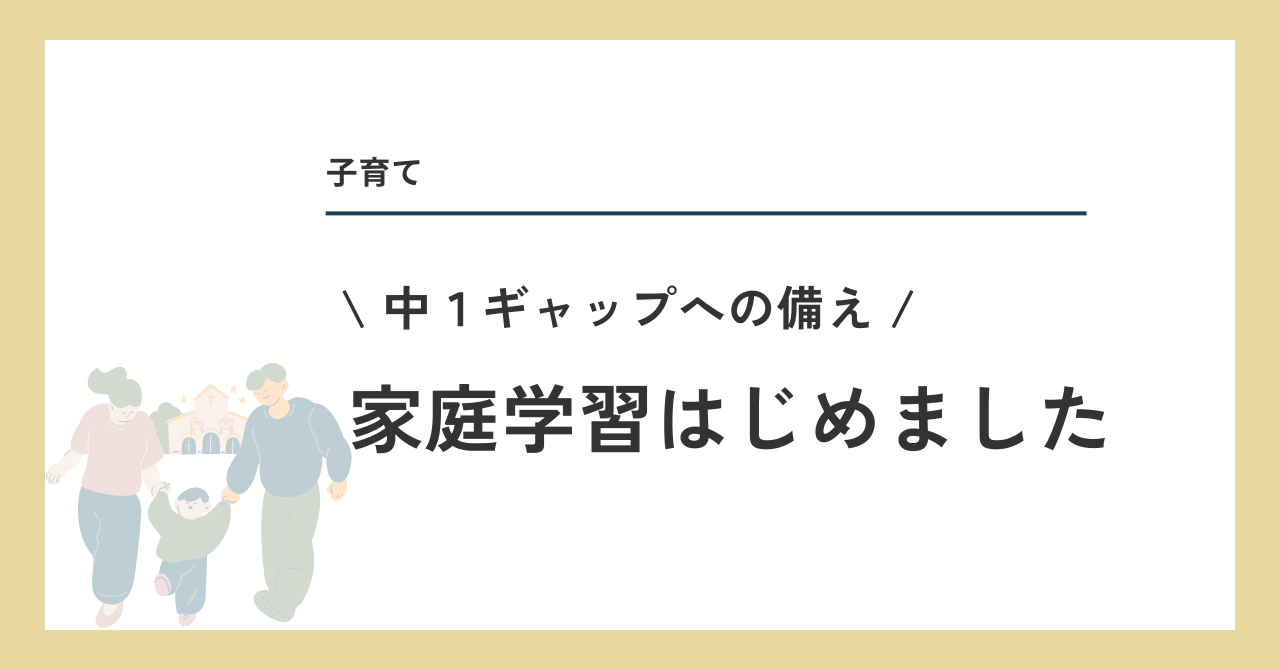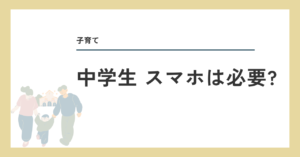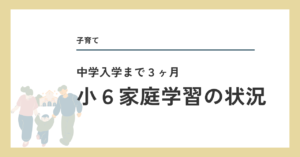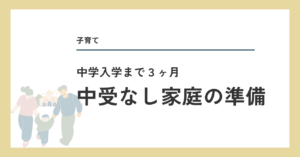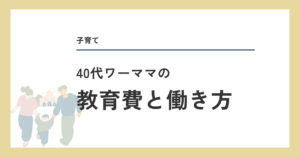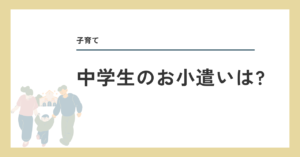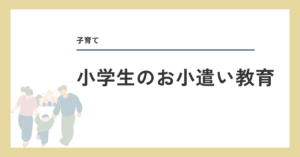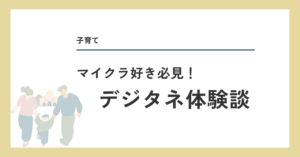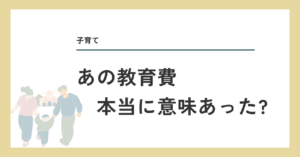はじめに
「中1ギャップ」という言葉を聞いたことがありますか?
小学校から中学校に上がるとき、多くの子どもたちが直面する「勉強や生活の変化によるつまずき」のことを指すそうです。勉強面だけでなく、部活が始まったり人間関係が変わったりすることで心身への負担も増える時期。
実は私も、今年になって初めて知った言葉でした。
きっかけは、ある日X(旧Twitter)で、「中1の英語って、小学校と全然違うよ。できる子とできない子に一気に分かれる」という投稿を見たこと。
これ、わが子のことかもしれない…。
でも、もっと焦ったのは、「うちって、そもそも毎日勉強する習慣がないじゃん…」ということ。
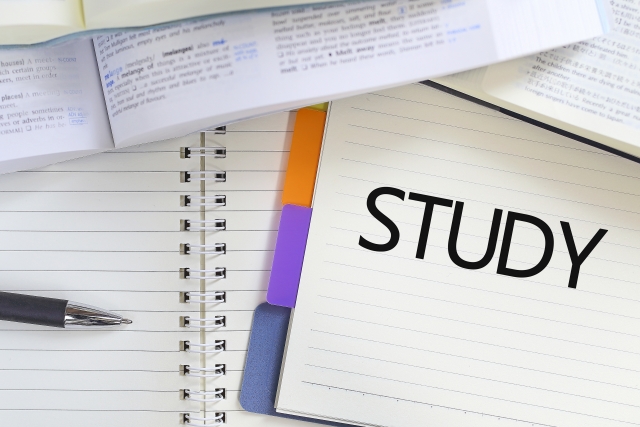
家庭学習を始める前の状況
わが家は息子の意向で中学受験をしないので、そこまで勉強に力を入れてきていませんでした😢
学校の宿題はきちんとやっているし、テストもそれなりに取れている。でも「宿題以外にも勉強する」という習慣は、まったくありませんでした。
中学に入ってから、急に学習スタイルが変わるとしたら…マズいかもしれない。
中学生になってから急に頑張るのではなく、あらかじめ生活の中に学習習慣を根付かせておくことが大切だと思い、小5の終わりごろから「中1ギャップに備えた家庭学習」を少しずつ始めることにしました。
ベネッセ教育情報の記事によると高学年の勉強の平均時間(宿題を含めた家庭学習)は78分とのこと。まずは短い時間から始め、少しずつ時間を増やしていければと考えていました。
まず意識したのは量より継続
小5まで、「勉強の習慣」がなかった息子。
いきなり長時間の勉強を求めるのはハードルが高いので、最初はとにかく続けることを優先しました。
- 時間は10〜15分でもいいから、毎日机に向かう
- できるだけ毎日やる時間を固定する(我が家は、習い事の日以外は夕食後が多い)
- 難しい問題集よりも、本人が気負わず進めやすい内容を中心にする
たとえば計算ドリルや漢字練習などシンプルなものから始めて、「今日もできたね」と一緒に確認しながらスモールステップで開始しました。
続けるための工夫
習慣化の最大の壁は三日坊主にならないこと。そこで、我が家では小さな工夫をいくつか取り入れました。
- 親も隣で見守る(別の作業をすることもありますが、聞かれたらすぐ対応できるように)
- 終わったら必ず一言「頑張ったね」と声をかける
- 週末は習い事の予定なども多いので、ぎちぎちに予定を組まない
このように、勉強内容の難しさよりもやり切れる環境づくりを意識したことで、本人もそこまで嫌がらずに続けられました。
習慣化がもたらした効果
数か月たつと、宿題以外でも机に向かうのが自然になり、息子自ら「今日、○時からやる?」と声をかけてきたりもするようになりました。やるのが当たり前という感覚が少しずつ身について来た気がしています。
ここで実感したのは、勉強を教えるよりも、まず環境を整えることの大切さ。親が横で一緒に机に向かうだけでも、子どもにとっては大きな後押しになるのだと感じました。
このあと、中編では科目ごとの準備や教材について書いています。
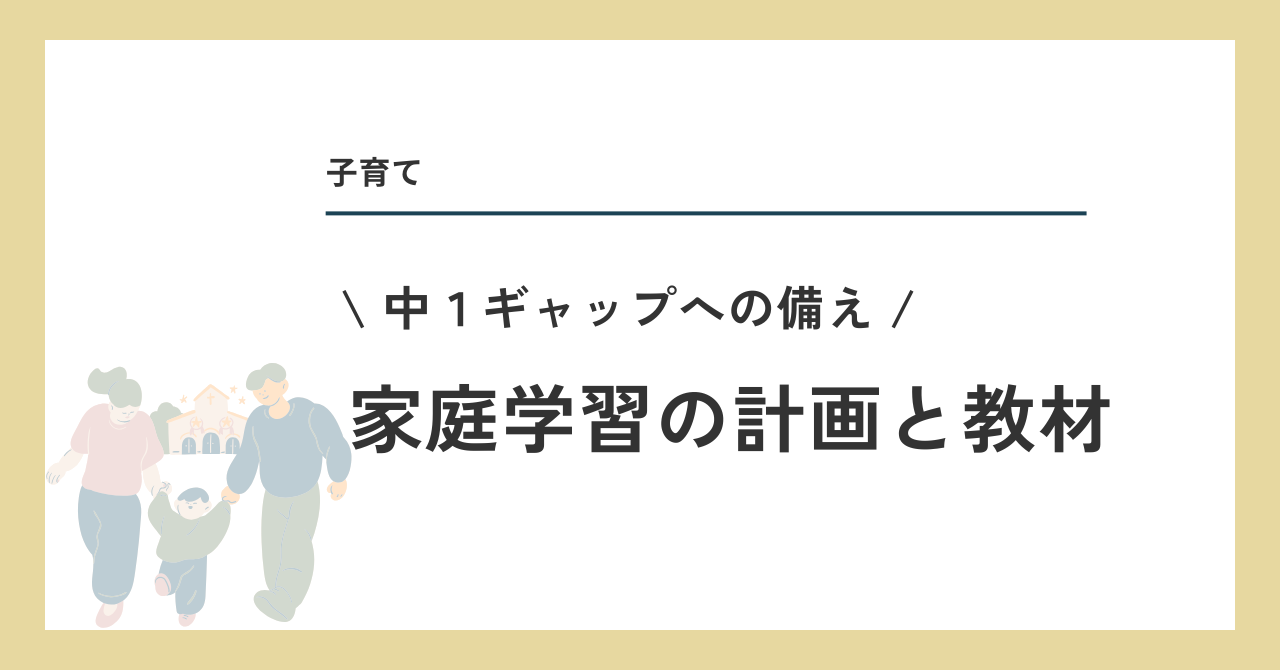
👉子育てのまとめページはこちら