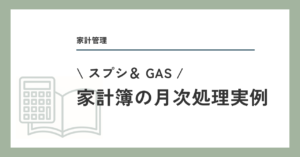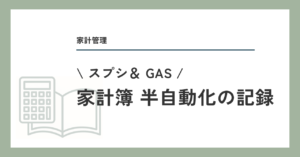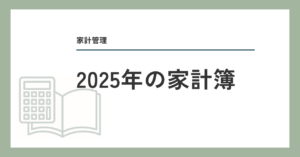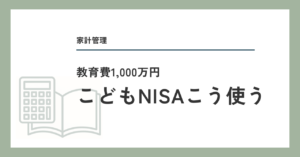はじめに
住宅ローンの返済を続けながら教育費も確保していく。老後資金についてもそろそろ気になる。
40代になると、この3つを同時に考える時期に入る家庭が多いと思います。
金利は今後の上昇リスクも気になる。
教育費はこれからが本番。
投資もできれば続けたい。
どれも大切な支出だからこそ、何を優先するかの判断が難しいですよね。わが家もその中で「住宅ローンをいつ、どんな形で返すか」を夫婦で話し合ってきました。
契約者である夫は、できるだけ早く返済して気持ちを軽くしたい派。私は、金利や教育費、資産全体のバランスを見ながら判断したい派。
今回は、そんな私たち夫婦が一括返済を視野に入れながら、どちらの選択にも対応できるよう備えている理由についてまとめてみました。

わが家の住宅ローンと現在の状況
わが家の住宅ローンは、2017年に借りた固定特約10年タイプです。
借入額は1500万円、金利は年0.55%。固定金利の水準としてはかなり低いところで借りることが出来たと思います。
毎月の返済は6万円台で、ボーナス返済はありません。
2027年に固定期間が終了し、住宅ローン控除も終わる予定です。このタイミングを節目に、一括返済か借り換えをして継続するかを決めることにしています。
一括返済については、家計全体のバランスを見ながら無理のない範囲で検討できる段階に近づいていますが、教育費や生活費とのバランスを考えると、慎重に判断する必要があります。
一括返済をためらう理由
金利が低い状況では、「住宅ローンを借りたまま資産運用を続けたほうが得」というのが一般的な答えです。私もそう思っていました。
ただ、実際に教育費がかかるようになってくると、現金を減らすことへの不安が出てきます。「得か損か」よりも、「気持ちの余裕をどう保つか」に考え方が変わってきたのを感じます。
もうひとつの理由は、今後の相場や金利の見通しが読めないこと。
特に金利は今後上昇していくことが予想されます。現在の金利が0.55%なので、いま変動金利で借り換えをしたとしてもそこまで金利は上がりませんが、長期的に見るとやはり金利上昇のリスクがあります。
一方で、一括返済をすれば現金は大きく減ります。教育費や生活防衛資金をどこまで残すかは、家計全体の安心感にも直結します。
夫婦の考え方の違いと、どう折り合いをつけたか
契約者である夫は「できるだけ早く返したい」と考えています。
その気持ちは理解できます。残高がなくなれば心理的にもすっきりしますし、毎月の固定支出が減る安心感は大きいものです。
私も、契約者の意向は大切にすべきだと思っています。
そこで私たちは、方向性としては一括返済を前提にしつつ、金利や生活状況の変化にも対応できるよう備えるという方針にしました。
教育費の山場が近づく時期と、固定期間終了が重なるため、どちらの選択でも家計が無理なく動くよう準備しておく。
それが、わが家なりの折り合いのつけ方です。
わが家の3年計画
2027年の固定期間終了を見据えて、次の3年間で少しずつ準備を進めています。
- 夫の新NISA積立は2026年で中断し、現金比率を高める
- 妻の投資資産の一部を段階的に現金化
- 緊急時には夫婦の個人資金から補えるよう話し合い済み
この3点を実行することにより家計全体の安定性が上がります。
「返したいときに返せる」「必要なら延ばせる」状態をつくることが、今のわが家にとって一番の安心です。
教育費とのバランスをどうとるか
住宅ローンの返済と並行して、大学進学までに約1000万円の教育費を準備する計画です。児童手当やジュニアNISAを活用し、残りは現金積立で補います。
住宅ローンを完済すれば、毎月の返済分をそのまま教育費として積み立てることもできます。一括返済を「終わり」ではなく、「次のステージの始まり」と捉えると、家計全体が少し前向きに見えてきました。
教育資金の準備については、以下の記事でもまとめています。
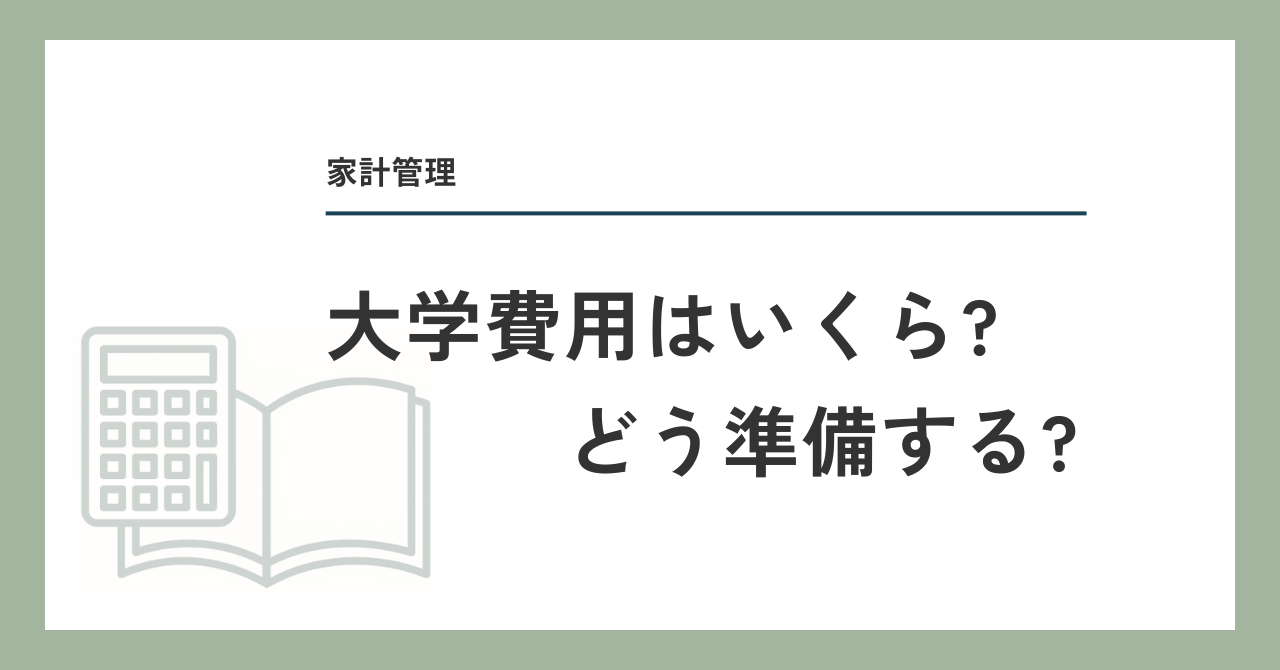
まとめ
住宅ローンを返すか、続けるか。どちらが得かよりも、どちらが安心して暮らせるか。
私たちは、一括返済を前提にしつつ、どんな状況でも家計が揺らがないように備えるという選択をしました。
今すぐ答えを出す必要はありませんが、2027年を迎えたときに納得できる判断ができるよう、これからの3年間、準備をしていこうと思います。
👉 家計管理のまとめページはこちら