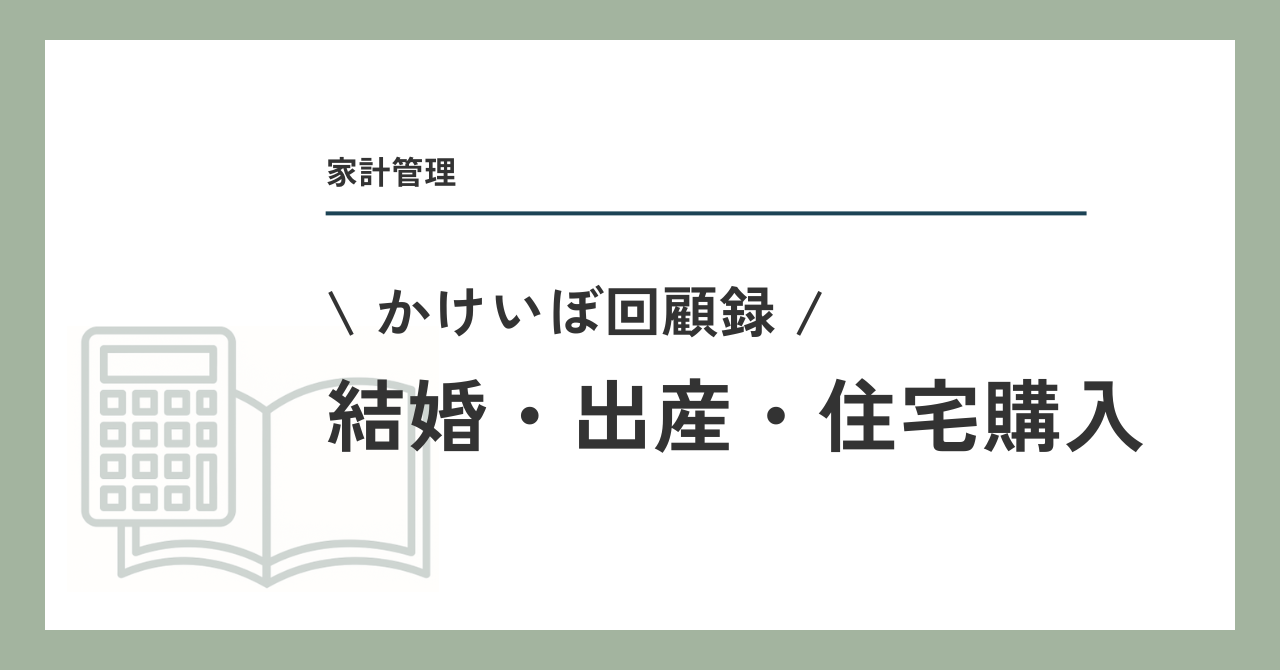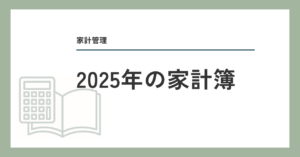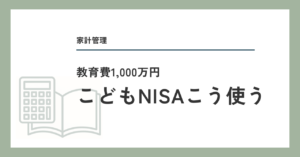はじめに
結婚、出産、住宅購入。
人生の節目を迎えるたびに、お金の流れも暮らし方も変わっていきます。
20年間家計簿を続けてきた中で感じるのは、生活の変化に合わせて家計を見直すことの大切さです。
今回は、2011年から2017年までのわが家の7年間、結婚・出産・育休復帰・住宅購入を経て家計簿をどう調整してきたかを振り返ります。

結婚時は「メリハリ」を意識した家計スタート
結婚当初の私たちは、使うところと抑えるところをはっきり分ける「メリハリ家計」を意識していました。
新婚旅行は一生に一度だからこそ、それなりに使う。その一方で、新居の家具や家電、日用品は必要最低限に。私の一人暮らし時代の家具家電をそのまま使い、購入費用は約60万円ほどに抑えました。
ちなみに、新婚生活実態調査2020(株式会社リクルートマーケティングパートナーズ)によると、結婚を機にインテリア・家具、家電製品を購入した新婚カップルの購入金額の平均は59.0万円とのこと。わが家のスタートは平均的だったようです。
新婚当時の家計管理については以下の記事でも紹介しています。
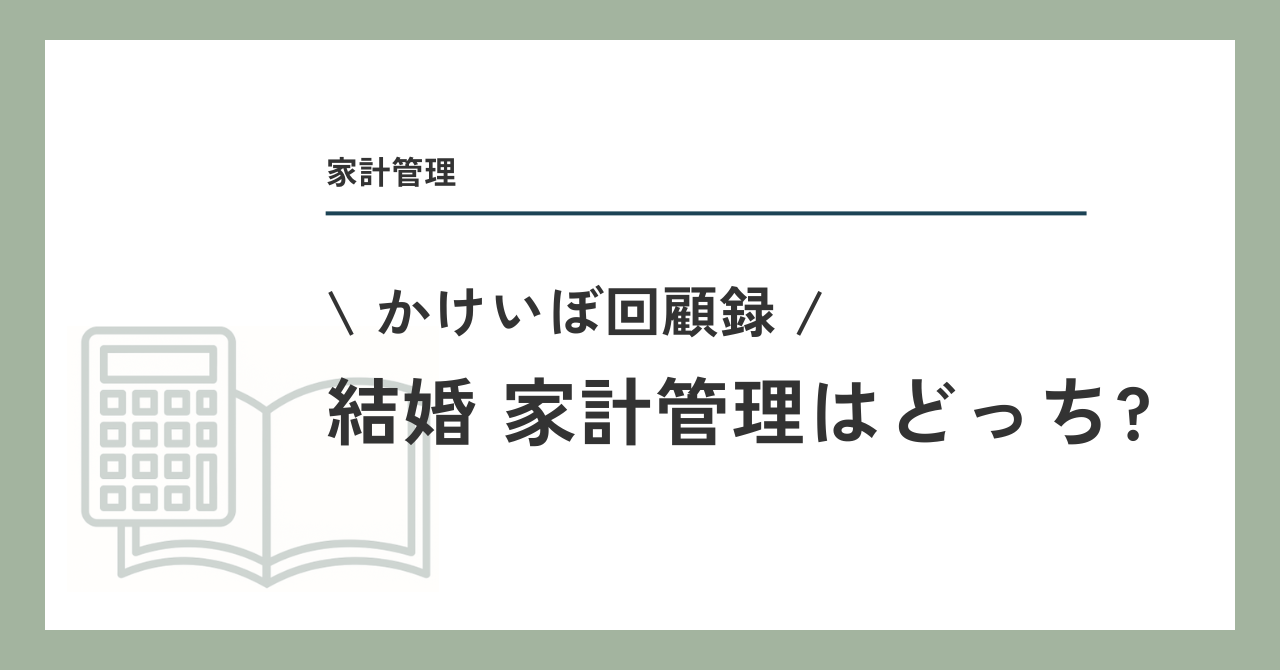
また、この時期に家計簿の形式も見直しました。
独身時代の個人管理から夫婦の収入と支出を一本化。さらに日常的な支出と特別費(1万円以上の不定期支出)を分けて管理するようにしました。これが今の家計簿の原型になっています。
妊娠・出産期は「安心や時間をお金で買う」
初めての妊娠・出産は、想像以上に心身が不安定でした。この時期は、「安心と時間をお金で買う」時期でした。
少し高くても、体に優しく安全な食品や日用品を選びました。体調が優れない時期は、宅配や惣菜にも頼りました。結果、食費は一気に前年比1.5倍の年間約70万円に。
でも、これは心の余裕や健康を守るための必要経費だったと思っています。
家計簿上では、大型の育児グッズ(消耗品以外)を特別費に分類しました。「一時的な支出」と「生活費の増加」を分けて記録することで状況を把握できました。
当時の私は必死でムダも多かったと思います。でも、あの時期の出費は今でも後悔していません。
育休復帰~保育園時代は「引き締め期」に
仕事復帰を控えた頃、家計簿を改めて見直しました。出産期に増えていた食費を中心に、無理のない範囲で引き締めを試みました。
その結果、前年に70万円まで膨らんだ食費は58万円(前年比約82%)に削減。節約というより、非日常を日常に戻すという感覚に近かったと思います。
この後に続く保育園時代は、子どもが熱を出すことも多く、遠出やお金のかかるレジャーは控えめでした。でも、地方ならではの豊かな自然や公園で十分に楽しめました。
お金をかけなくても思い出は作れる、それを体感したのがこの頃です。
住宅購入後は固定費に注意
住宅を購入したのは、子どもが保育園の年中の頃。住宅ローンについて夫婦で一致していたのは、「無理のないローン」と「固定金利」。
ローン返済額は、賃貸時代の家賃と同程度に設定しました。一方で、戸建ては固定費(光熱費や通信費)が上がりやすいので、まずはプランの見直しや使い過ぎ防止を意識しました。
結果、ガス代はプロパンから都市ガスになって減少。電気代・水道代は少し上がったものの、トータルでは年間+約2万円に収まりました。
また、ネット回線と格安SIMをセット契約に切り替えて通信費を年間6万円削減。家計簿で固定費を定点観測することで、生活コストを過度に膨らませずに済みました。
家具や家電も、新居に合わせてすべて買い替えたい気持ちをぐっとこらえ、使えるものはそのまま使用し購入費用は約60万円で抑制。
まとめ
この7年間を振り返ると、ライフイベントごとに数字と向き合ってきたことで、お金だけでなく暮らし全体を少しずつ整えられた気がします。
変化に柔軟でいられること、それが家計簿を続けるいちばんの価値かもしれません。
👉 家計管理のまとめページはこちら