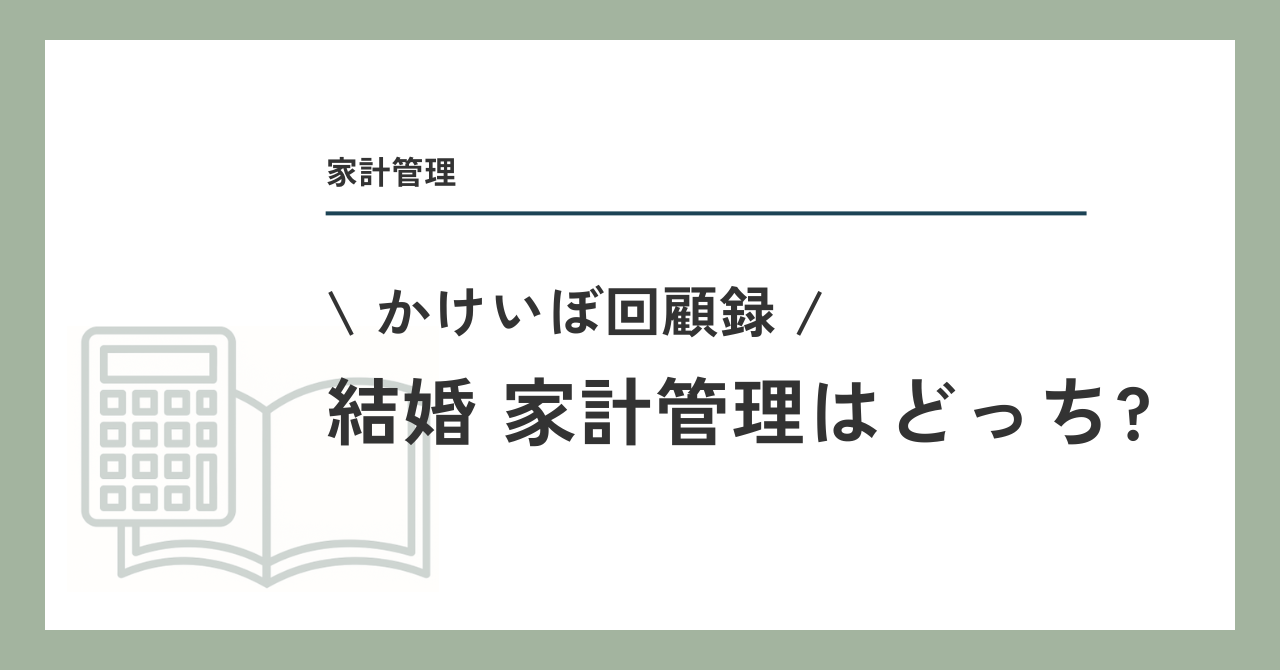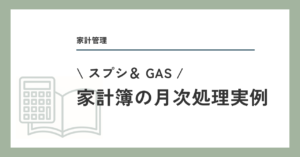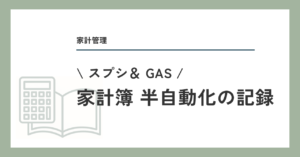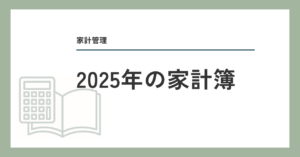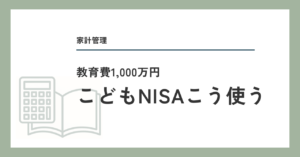はじめに
結婚したばかりの頃、意外と多くの夫婦がぶつかるのが「家計管理をどちらがやるか」という問題です。
わが家も例外ではなく、結婚当初は「お互い堅実派」だからこそ、どちらが家計を担うかでちょっとした静かな攻防がありました。
この記事では、当時のわが家のエピソードをもとに、夫婦で家計をどう分担するか悩んでいる方へヒントになればと思います。

結婚当初、どちらも「自分がやりたい」と譲らず
当時の私たちは共働きで、貯蓄額も年収もほぼ同じ。お金の使い方にも大きな差はなく、性格的にもどちらかといえば「堅実派」でした。
そんな私たちですが、いざ「結婚後の家計をどうするか」という話になると、どちらも「自分が管理したい」と譲らず。
私は一人暮らし経験もありその当時すでに家計簿歴は数年。少ない収入の中から奨学金の返済も経験し、家計管理にはかなり自信がありました。
-10.jpg)
一方、夫も同じように「自分もきちんとしている」と思っていたようで、しばらくは膠着状態が続きました。
家計簿を見せて信頼を得た瞬間
最終的に私が取ったのは、「実績で説得する」という方法。
独身時代に続けていた家計簿を夫に見せ、「お金の使い道は必ず相談するし、透明に管理する」と伝えました。
さらに、結婚前後のイベント(結婚式や転居費用、新婚旅行など)では、私が率先して予実管理を担当しました。予算表をExcelでつくり、「この範囲でやれば予定内に収まる」というのを見える化し、費用も折半。
加えて、結婚後の2人暮らし生活費も事前にシミュレーション。「1か月いくら貯められるか」を試算してそれぞれの貯蓄口座に同額ずつ積み立てる方法を提案しました。
こうした「数字で見せる」姿勢が、最終的に夫の同意を得るきっかけになったのかなと思います。
その後の夫婦の資産形成については以下の記事でも詳しく書いています。

結婚初期に家計管理を決めるときのポイント
振り返ってみると、「どちらが管理するか」には正解がないと思います。共働きでも「別財布」「共同財布」など家庭によって本当にさまざま。
ただ、私自身の経験から言えるのは、管理する側は以下の点を意識するといいのではないでしょうか。
- 透明性:記録を開示し、支出を共有する
- 公平性:どちらかが損・得を感じない仕組みにする
- 継続性:1年など一定期間で見直す余地を残す
特に「透明性」は、信頼を築くうえでいちばん大切。お金の管理は、相手に不安を与えると一気にこじれてしまう可能性があります。
📌 わが家の家計簿シリーズ
まとめ
今思えば、当時の私が信用してもらえた理由は、「お金の流れをきちんと見せる」「相談しながら進める」姿勢を見せることが出来たためだと思います。
もし今、結婚後の家計管理で悩んでいるなら、家計管理のイメージを共有してみるのもおすすめです。
👉 家計管理のまとめページはこちら