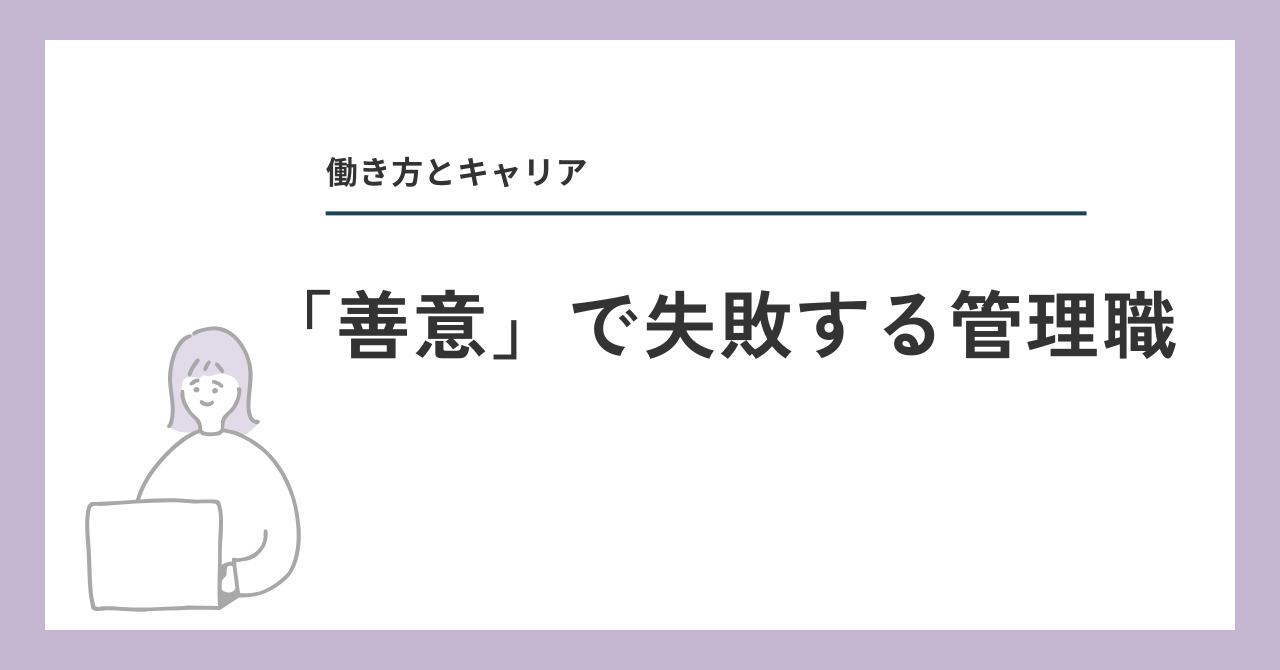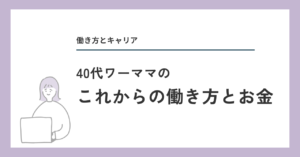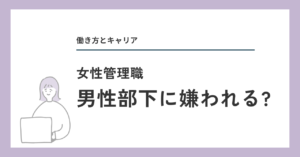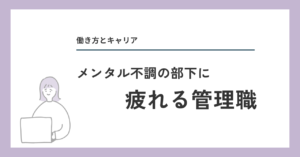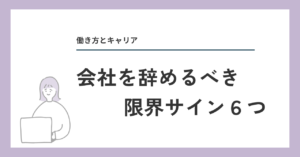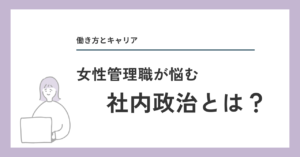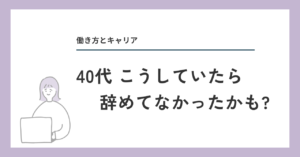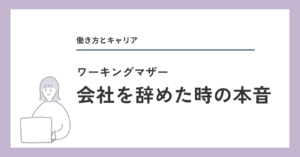はじめに
「ワーママ管理職体験記」で管理職時代の苦労話を書いています。
今回もその一つ。
人のために動いたつもりが、なぜか関係がぎくしゃくする。正しさや責任感を前に出すほど、自分も周囲も疲れてしまう…といった経験。
管理職として働く中で、私が何度も向き合った現実です。
善意が裏目に出た2つの事例をもとに、周囲との関わり方や「ちょうどいい距離」について考えます。
ケース1 善意の押し売りで関係が冷えた

遅れていた部下の資料づくりを見かねて、私が先回りして手を入れたことがありました。
早く仕上げたい思いから、要点整理や章立てまで整えて渡したところ、相手は黙り込み、その後どんどん口数も減っていきました。
後で知ったのは、私の行為が助け舟ではなく介入として受け取られていたこと。自分のやり方を否定されたように感じたのだと思います。
- 相手が助けを求める前に先回りして動かない
- 援助と介入は紙一重だと忘れない
仕事の納期や品質は大切ですが、相手の自尊心を削ってまで得るやり方はダメだと学びました。
ケース2 仕事を避ける管理職との板挟み
難しい案件を他部署から丸投げされたことが続きました。
現場の混乱を前に、私はつい受け止め役に回りがちでしたが、結果的に部下からも不満の声が…。相手の管理職に正しさを訴えても動かず、調整のたびに心がすり減っていきました。
- 正しさだけではどうにもならない場面がある
- どこまでが自分の責任かを冷静に線引きする
全て抱え込むほど、チームの主体性も私自身の余力も失われていきます。
善意も責任感も万能ではない
二つの場面に共通していたのは、現状を打破したいという私なりの責任感でした。
けれど、善意も使いどころを誤ると、悪い方に作用することがあります。
私もついつい正論で考えがちでしたが、それより、状況を整え相手が動ける土台をつくること。そのほうが遠回りに見えて、結局は成果につながると感じます。
まとめ
誠実に働く人ほど、全方位への配慮で自分をすり減らしがちです。
けれど、関わりすぎても、離れすぎても、仕事はうまく回りません。
私が今になって思う答えは「適度な距離を保つこと」です。
がんばりどころと手放しどころを見極めること、それが管理職としての大事な姿勢だと今は思います。
👉 働き方とキャリアのまとめページはこちら