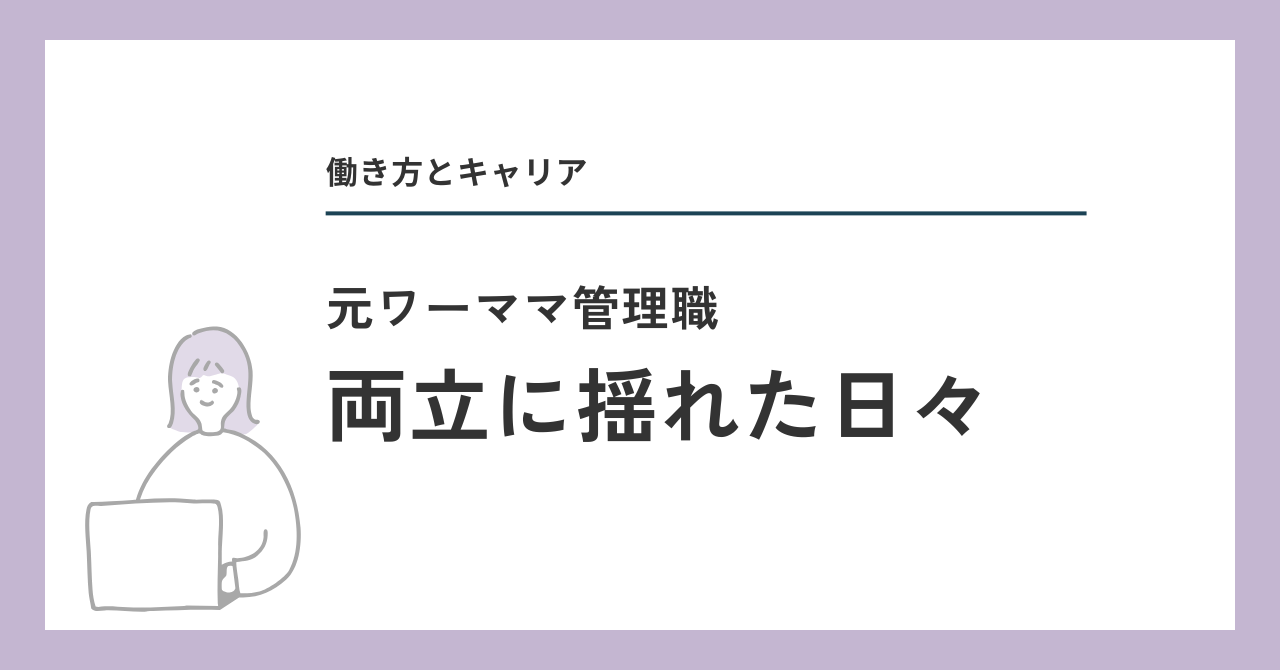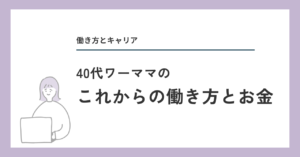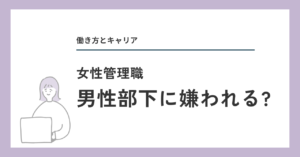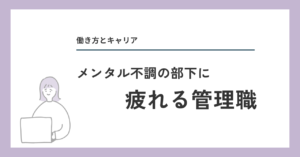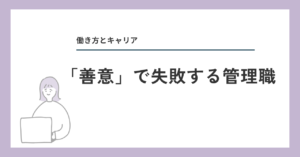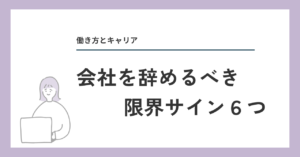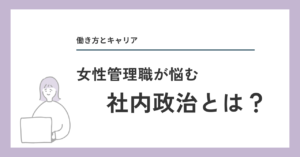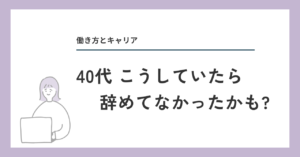はじめに
ワーママとして管理職を続けていると、「もう疲れた…」と思う瞬間があります。
子どものこと、職場のこと、責任と制約の狭間で心も体もいっぱいいっぱい。私自身も管理職として働いた数年間で、何度も「このまま続けられるだろうか…」と揺れました。
責任のある立場だから弱音は吐けない。でも、家に帰ると何もできなくなる。そんな状態が続くと、「私だけが弱いのかな」と思ってしまいます。
この記事では、実際に疲れを感じた理由と体験、そして考えた選択肢についてお伝えします。
もし今、「管理職になってから疲れた」ではなく、「管理職への打診を受けようか迷っている」という段階なら、こちらの記事が先に役立つかもしれません。私が打診を受けたときの迷いと、上司にどう返事をしたかをまとめました。
👉 昇進打診を受けたときの迷いと返事のしかた
ワーママ管理職が疲れる理由「責任と家庭の両立プレッシャー」

管理職という立場は、責任と時間の両面で負荷が大きいものです。ワーママの場合はさらに、次のような要因が重なりやすいと感じました。
- 成果責任や部下育成のプレッシャー
- 会議や調整業務が急増し、時間が圧迫される
- 子どもの急な体調不良や学校行事への対応
どれか一つなら乗り越えられても、同時に起きることで限界を感じやすくなります。
私がしんどさを強く感じた場面
周囲に弱みを見せられない
課長になったとき、部下の多くは自分より年上でした。
そして、「女性管理職」や「時短管理職」という立場だったからこそ、弱みを見せてはいけないという気持ちがいつもありました。
一部の部下には「年下の女性上司」に抵抗を示す態度もあり、正直やりにくさを感じました。
当時の私は「認めてもらうには成果を出すしかない」と思い、背伸びして頑張りすぎていました。成果が出るまでは常に緊張感があり、消耗も大きかったです。
子どものことでしか休めず、自分を追い詰めた
子どもの体調不良で職場を休むことが多くなるため、自分の体調不良では休めないと考えていました。
私が管理職になったのはコロナ前でしたので、自分のことでは休みにくい雰囲気も正直あり、自分を追い込んでいました。
ところが、その無理がたたって大事なイベントで穴をあけてしまったことがあります。
「自分は管理職に向いていないのでは」と強く落ち込みましたし、同時に、このような働き方では次世代の女性に「やっぱり無理だ」と思わせてしまうと反省しました。
管理職時代の苦労話
- 管理職は「善意」で失敗することもある|私が学んだ周囲との関わり方
- メンタル不調の部下を支えて感じた虚しさ|がんばる管理職ほど疲れてしまう理由
- 女性管理職は男性部下に嫌われる?|嫉妬を恐れずフラットに働くために
支えになったもの
それでも続けられたのは、いくつかの支えがあったからです。
- 上司が柔軟な働き方を認めてくれたこと
- 夫が家事や育児をさらに担ってくれたこと
- 同僚や後輩が応援してくれたこと
こうした周囲の理解や支えがあったからこそ、疲れを感じても「もう少し頑張ろう」と思えました。
続ける・降りる・辞める、3つの選択肢
管理職の打診を受けた際、考えていたのは「できなければ降りればいい」ということでした。そして、この考えは管理職として働きながらいつも頭の片隅にありました。
- 続ける場合
-
まずは制度を活用し、周囲にサポートを求めながら工夫する。
私は最初から「時短管理職」ではありましたが、フルタイムの方の場合、制度があり状況が許すのであれば、ペースダウンを交渉してもいいかもしれません。 - 降りる場合
-
役職から降りる選択もあります。私の当時の勤務先では、「部下なし管理職」があったので、望めばそのポジションになったと思います。一方で、管理職を降りる=一般職に戻る、という企業もあるかもしれません。いずれにしても責任を軽くすることは、心身を守る意味で効果的だと感じます。
- 辞める場合
-
転職やフリーランスなど新しいキャリアに踏み出すこともできます。今の私がまさにそうです。
「続けるか、降りるか、辞めるか」といった具体的な選択肢を考える前に、一度気持ちや状況を整理したい方はこちらの記事も参考になさってください。
👉 40代ワーママ 仕事を辞めたいときの判断基準と対処法ガイド
まとめ
ワーママ管理職は確かに疲れます。責任も制約も大きく、無理をして続ければ心も体も持たなくなります。
けれど「続ける」「降りる」「辞める」、どの選択肢も間違いではありません。
大事なのは、自分と家族にとって納得できる働き方を選ぶこと。
同じように疲れを感じている方に、「一人で抱え込まなくて大丈夫」と伝えたいです。
👉 働き方とキャリアのまとめページはこちら