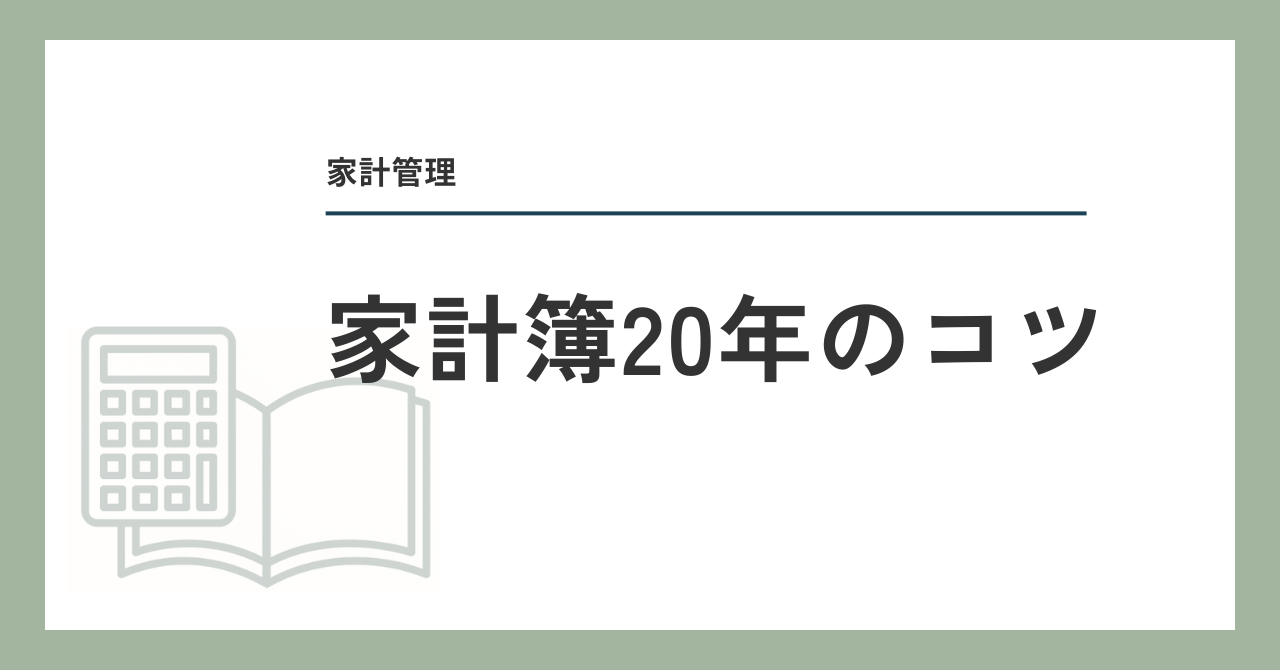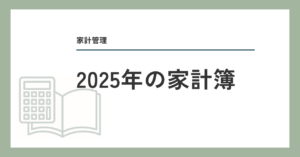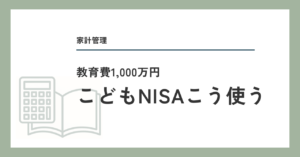はじめに
💡 このページは、家計管理カテゴリ全体の「まとめページ」です。
「家計簿をつけ始めたけれど続かない…」そんな経験、ありませんか?
実際、最近の調査では「日常的に家計簿(アプリ含む)をつけている」と回答した人はわずか15.1%にとどまるそうです。(生活定点1992-2024より)
我が家は40代夫婦と子ども1人(小6)の3人家族。地方在住です。
社会人一人暮らしの頃から、結婚、出産、フリーランス転身。形を変えながらも、気づけば20年ずっと家計簿を続けてきました。
この記事では、家計簿を続けるためのコツと、わが家の家計管理の方法をまとめました。

家計簿が続かなくなった時期と、私がやめた理由【体験談】
家計簿を20年つけている私も、一度家計簿をつけるのを中断していた時期があります。2018〜2019年頃のことです。
もともとは毎週末にレシードなどの支出を整理し、毎月の収支を出していました。当時は現金払いも多く残金を合わせるのが地味に大変でした。
育休復帰後も忙しいながらなんとか続けていましたが、子育てと仕事の両立が落ち着いてきた頃、ふと「もう生活費も安定してるし、つけなくてもいいかも」と感じ、定期的な記録はやめてしまいました。ただ、クレカや通帳の履歴は残していたので、年間の収支は後からまとめることができました。
そして2020年。
コロナ禍の自粛生活で「出費も減ったはず」と思って確認してみたら、思ったほど減っていなかったんです。このとき、「やっぱり感覚だけではわからない」と痛感し、記録を再開するようになりました。
家計簿を再開してからは、項目を以前よりシンプルに、そして月単位ではなく季節ごと(四半期)に全体を把握するように。「だいたいの傾向が分かればOK」と思えるようになってから、また続くようになりました。
一度やめた時期があったからこそ、「どうすれば自分の暮らしに合う形で続けられるか」を見つけられました。
家計簿を続けるための5つのコツ
上記のような中断期もありながら、家計簿を20年間続けてこられたのは、試行錯誤の結果、自分に合ったスタイルを見つけたからです。
ここでは、私が無理なく家計簿を続けるために取り入れている5つの工夫をご紹介します。
完璧主義をやめる
最初から「1円単位まで合わせる」と構えると長続きしません。私はざっくりと項目ごとに記録することからスタートしました。
管理項目も、細かくしすぎるときりがないので、支出だったら「食費・生活用品」「水道光熱費」「通信費」くらいの大まかな分類にすることで、毎回の入力がとてもラクになります。
細かいところは気にせず、「続けること」自体に価値を置いたのがポイントでした。
自分好みのツールを探す
家計簿アプリもいろいろ試しましたが、私には自由度の高くシンプルなExcelが一番合っていました。
必要な項目だけ、自分にわかりやすい形で入力できるのがポイント。手書きよりも手軽で、見返しやすいのもメリットです。
データを有効活用
私が家計簿を始めた頃はまだまだ現金払いが多かったですが、最近はクレジットカードや電子マネーの利用をメインにすることで、利用履歴が自動で残ります。
今は、半期に一度、明細をダウンロードし内容を確認して項目別に集計するだけ。作業時間としては2~3時間程度です。
振り返りタイムをつくる
集計が終わったら、家計簿を見ながら「今回の期間はどうだった?」と振り返る時間を持っています。
目標とのズレや、自分の気持ちの変化にも気づけるこの時間が、継続のモチベーションにもつながっています。
無理な目標は立てない
振り返りを行った後は、翌年の予算を項目別に設定しています。
ですが、例えば「今年は外食費が多かったから、来年の予算は半減!」などの無理な目標は立てません。最低ラインとして「昨年以上に増やさない」ことを目標としています。無理な目標を立てても達成が難しいことがわかっているからです。
全体でバランスがとれていればいい。そう思うようにしています。
家計簿をつけることは自分の暮らしを見つめ直す習慣。この5つの工夫があるからこそ、ここまで続けてこられたのだと思います。
現在の家計管理スタイル
フリーランスになった今も、家計管理の基本の形は会社員時代から大きくは変わっていません。
フリーランス収入は私の口座、夫の給与は夫の口座に入金されます。月々の生活費は主に夫の口座から、特別費は私の生活費口座から出すという仕組みで、会社員時代から続けてきました。
私は家計全体の管理を担っていますが、通帳やカードの管理は夫に任せています。
すべてを自分一人で抱え込まず、役割を分けることでストレスなく続けられるし、家計管理の公平性・透明性のためにもある程度分担するのが健全だと思うからです。
家計簿に対する考え方
家計簿は「お金を貯めるための道具」というより、「どう生きたいか」を考えるためのきっかけだと思っています。
もともとは、私が家計簿をまとめて夫に結果を報告し、「今後どう使うか」を相談していました。
最近は子どもも成長し、買い物やレジャーの計画を一緒に話すようになり、家族みんなで暮らしの価値観を共有する場になってきています。
家計簿は数字を管理するだけではなく、家族の会話を生み出すツールにもなっているのです。
家計簿が支えてくれた変化
振り返ると、家計簿は数字の記録以上に「暮らしのあり方」を支えてくれる存在でした。
収入が少なかった20代も、家計簿があったからこそお金への不安に飲まれずに済んだと思います。
今はフリーランスとして収入が変動する日々ですが、家計簿を見返すことで「どんな状況でもやっていける」という安心感があります。
家計簿が続かない時期があっても大丈夫。
私自身も、やめた経験があったからこそ、自分に合ったより良い管理方法を見つけられました。
家計簿は、私にとって 「暮らしをコントロールする自信」 を育ててくれた大切な習慣。これからも、ゆるく長くつき合っていけたらと思います。
関連記事まとめ
ここからは、家計管理に関する記事をテーマ別にまとめています。
興味のあるテーマからチェックしてみてください。
🧩 家計簿の仕組みと考え方
- わが家の家計簿|支出項目と公開のルール
- 銀行&証券口座の使い分けルール|夫婦+子どものお金管理法
- 家計簿をスプレッドシートで作る|クレジットカード中心のわが家の実例
- 【2026年予算】月次予算の立て方
- 【2026年予算】特別費予算の決め方
- 我が家の支出は適正?総務省家計調査と比べてみた
- わが家の保険を全部公開!入ってよかった・やめてもよかった保険
- 40代夫婦が考える住宅ローン完済のタイミング
- 40代フリーランス|金融所得と国保の話
💰 リアル家計簿
📓 かけいぼ回顧録
- 家計簿は人生の記録。原田ひ香さんの『彼女の家計簿』を読んで思ったこと
- 2011|結婚、どちらが家計管理するか問題
- 2011〜2017|結婚・出産・住宅購入で変化した7年間
- 2018〜現在|夫婦で違う家計の価値観と付き合う方法
- 2022〜2023|会社を辞めて見直した支出・見直さなかった支出
🎒 子どもにかかるお金を知る
- 子どもが一人増えて月々の生活費はどうなった?
- 小学生の教育費、平均と比べてどうだった?1歳〜小6までの実データと徹底比較
- 中学から増える生活費をどう見積もる?わが家のシンプルな方法
- 給食費無償化はいつから始まる?誰が対象?家計負担がいくら軽くなるか検証
- 【教育費シミュレーション】中学生にかかるお金を文科省データでチェック
- 【教育費シミュレーション】高校生にかかるお金を文科省データでチェック
- 【教育費シミュレーション】大学進学には1,000万円必要?実際の平均額とわが家の備え方
- 教育費1,000万円の備え方|こどもNISAがあったら わが家はこう積み立てる
🍃 関連テーマのまとめ記事
まとめ
家計簿を続けることは、数字の管理だけでなく、暮らしの変化や気持ちの記録でもあると感じています。
お金の使い方には「正解」はなく、その時々の家族の状況に合わせて見直していくもの。
このまとめページが、「家計簿をつけたいけど続かない」「教育費が不安」「保険を見直したい」そんな方のヒントになればうれしいです。