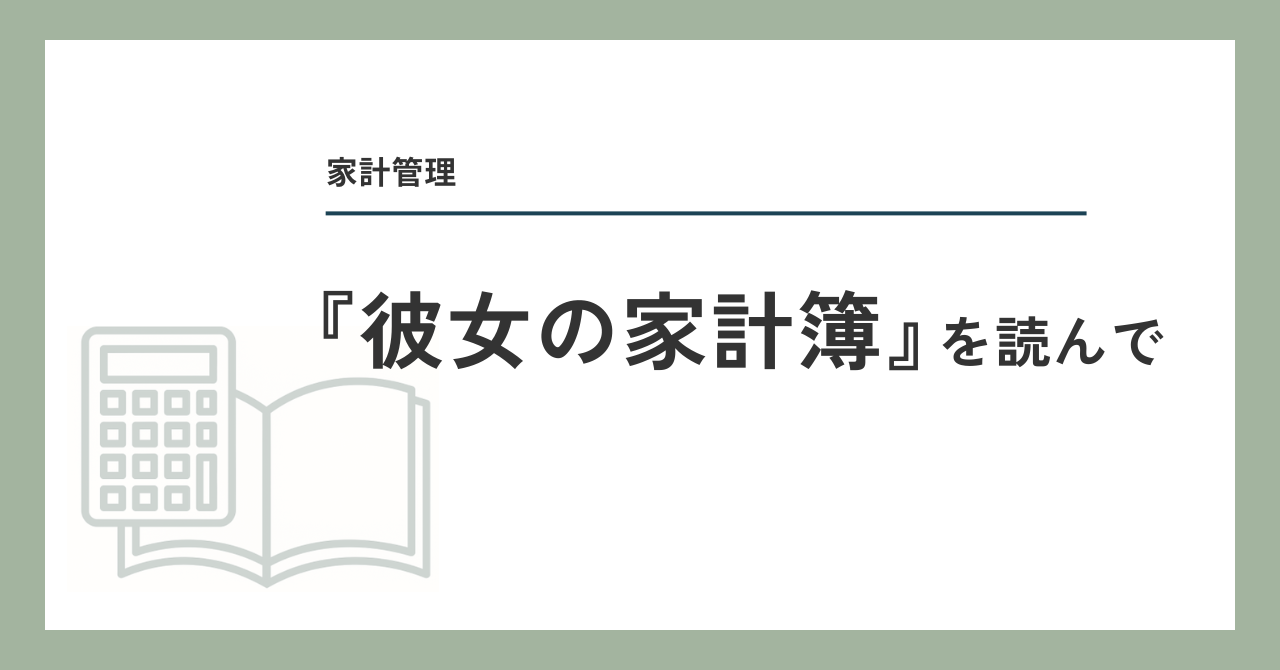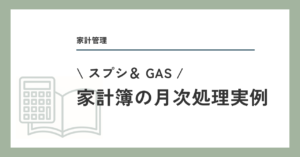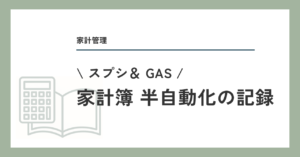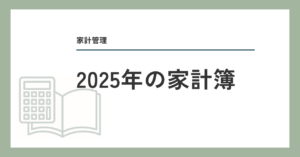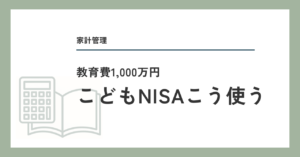はじめに
本屋さんでふと手に取った、原田ひ香さんの『彼女の家計簿』。
三世代の女性たち(祖母・母・娘)の人生が、「家計簿」を通してつながっていく物語です。
10年ほど前の作品ですが、読んでみたら、主人公の年齢が当時の私とほぼ同じ。
子どもが生まれたばかりの頃の気持ちや、母との距離感などが自分の過去に重なって、思いがけず胸に刺さりました。
家計簿にあらわれる人生

印象的だったのは、「家計簿には、その人の人生観や生き方が表れる」というこの本の土台となっているであろうテーマ。
そして、主人公の祖母がつけていた家計簿が、時代を超えて娘や孫に届き、断絶したと思われていた家族の物語をつなぐきっかけになるところです。
主人公の祖母が、「仕事を辞めていい」と言われたときに、「私は仕事を続けたい」と自覚するシーンもありました。当時の人々にはなかなか理解されなかった価値観だったと思います。
今は無理でも、いつか誰かがわかってくれるだろう。そんな時代が、きっと来る。
その一言が、今を生きる私の胸にも響きました。
そして、私自身の祖母のことも思い出しました。
あぁ、おばあちゃんに会いたいなぁ…。おばあちゃんは、どんな思いで、生きて・働いていたのかなぁ。
数字から思い出す暮らしの記録
私も、気づけばもう20年も家計簿を続けています。
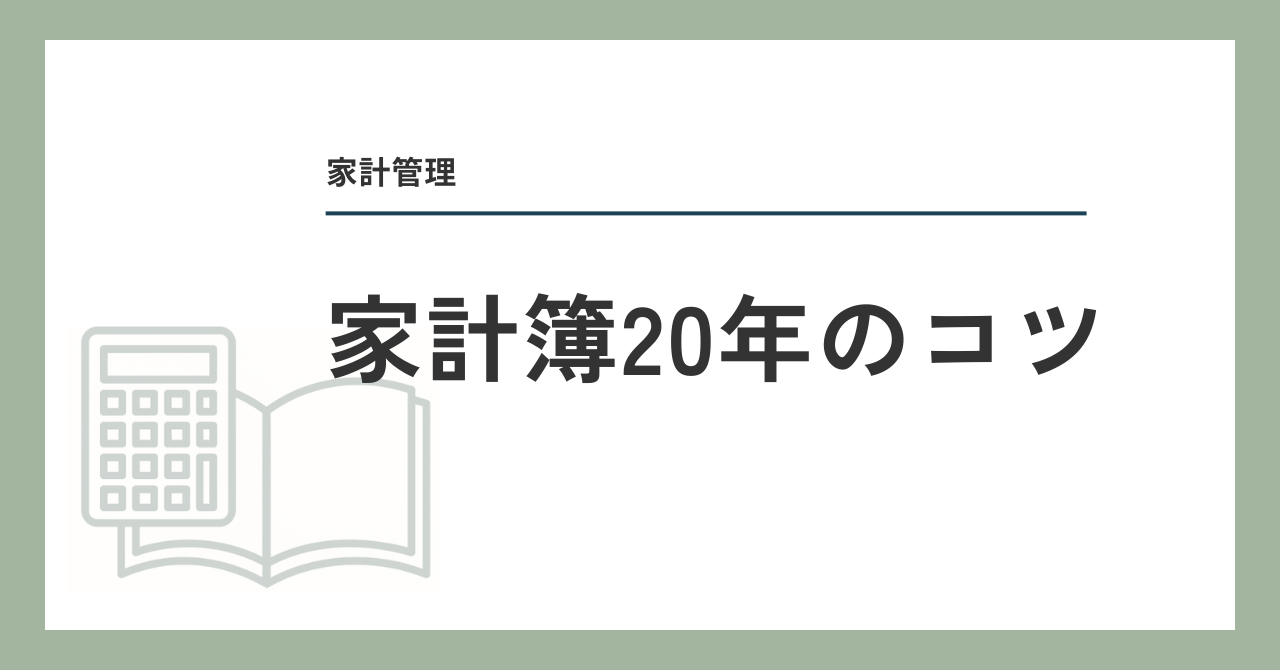
私自身は、この小説のように家計簿に日記を書き残すタイプではありませんが、当時の数字やメモを見返すと、そのときの暮らしがよみがえります。
医療費が多かった時、外食費が増えた時、旅行にたくさん行った時。
家計簿を振り返ると、不思議とその時の空気感まで思い出せるのです。数字を並べているだけのようで、実は「暮らしを重ねてきた証拠」そのもの。
それが私にとっての家計簿の魅力なのだと思います。
まとめ
『彼女の家計簿』を読んで感じたのは、家計簿って単なるお金の記録ではなく、生き方の記録でもあるということ。数字の裏に、選んだもの・我慢したこと・支え合った日々が全部詰まっている。
これからも、今の自分を映す鏡として、家計簿と向き合っていけたらと思います。
追記:かけいぼ回顧録、はじまります
この作品をきっかけに、私自身の家計簿の振り返りを「かけいぼ回顧録」としてまとめていく予定です。
本のようなドラマティックな物語はありませんが、これまでの記録の中には、子どもが生まれた年、家を購入した年、仕事を辞めた年。数字とともにいろんな節目がありました。
📌第一弾はこちら

今後、過去の家計簿の記録を少しずつ思い出しながら、暮らしとお金の歩みを、自分らしい言葉で残していけたらと思います。
👉 家計管理のまとめページはこちら